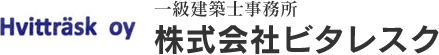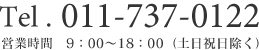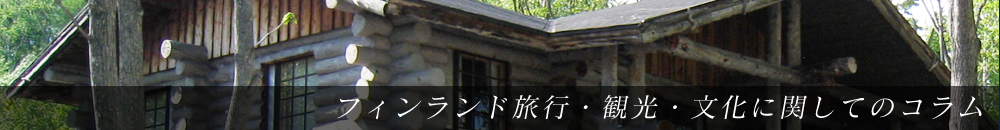2016-04 marimekko
フィンランドの出張の帰りには、私は、いつもヘルシンキのmarimekko マリメッコへ 寄って、妻に服を買います。長年やっているので、年配の店員さんとはすっかり顔なじみです。私の顔を見つけると必ず、XSありますよと声をかけてきます。妻は、小柄なのでフィンランド人のSでもおおきすぎるからです。そんなマリメッコも長年のエスプラナーディ通りからミコン通り、アレキサンテリン通りへと店を移しています。ストックマンデパートの隣の前面一部平屋の店は、1960年代からNISSENという店で、五木寛之の初期の作品『青年は荒野を目指す』という小説の中にも、登場していました。どこか昔を懐かしめる建物でしたが、いつの間にかマリメッコに変わっていました。又一つ、古い店がヘルシンキから消えてしまいました。今、若い人ならみんな知っている、日本でも20店舗以上あるマリメッコですが、フィンランド語では、第一音節の母音にアクセントが来ますから、余計なことですが、正しい発音は、マリメッコです。
わが家の愛犬は、バンダナをしています。子犬の時は首輪ですが成犬になってからは、いつもバンダナです。先代の犬から続いています。色違いのマリメッコのバンダナを使っているのですが、結構ぼろぼろになります。買い物ついでに、新しいバンダナを買おうと思ったのですが、しばらく来ていないせいか、見当たりません。週末、暇でしたので、ヘルシンキ中心部のマリメッコのショップをいくつか見て回りましたが、見つかりません。仕方なく店の人に尋ねると、そのバンダナはもうありませんとの、そっけない返答。言葉に困っていると思ってくれたのか、シルクのバンダナはいかがですか、とイントネーションに違和感のある日本語で別の店員に奨められましたが、野原を駆け巡る犬にシルクはないでしょう。埒が明かないので、中心部を少し離れたItäkeskusを思い出し、地下鉄で8駅目まで足を伸ばしてみました。ショッピングモールは、にぎわっていましたが、目指すバンダナは、ここのマリメッコにもありませんでした。仕方なくキーボードをたたいて調べてもらうと、アウトレットに黒だけは在庫があると教えてくれました。又、地下鉄に乗って今度は、Herttoniemiまで逆戻りです。駅から徒歩で5分ほど、ようやくUnikko柄の黒のバンダナを手に入れることが出来ました。無くなってしまっては又、大変と3枚買いましたが、本当は赤か緑が希望でした。犬のためにこんなに時間を使うのはおかしな話ですが、普段歩かない、いろいろな地区の町並みを眺めたり、郊外は地上を走っている地下鉄の車窓からの景色も、新鮮で結構楽しい時間を過ごしました。
2016-03-2 トラム沿線2
ヘルシンキ駅より地下鉄に乗って、北方向へ移動しました。最初の駅がまずKaisaniemi から、ヘルシンキ大学に駅名が変更されていたのに少し驚きました。次の駅hakaniemiで地下鉄を降り、地上に出てトラムのライン9に乗換えて、イタパシラ(東パシラ地区)へと向かいました。数年前、このトラムに乗った時は、どんよりした天候で寒さも加わって、少し昔を思い出して感慨にふけった景色でしたが、40年前の最先端地域が、どのように変わっているのかを、じっくりと冷静に見てみようと思いました。
建物群全体は、さほど古びることなく、かといって華々しく発展している風もなく、いかにもフィンランドらしい、静かに時が経過している姿でした。
パシラ駅から西側を望むと、昔の記憶にはなかった住宅、オフィスビル郡が、東と同じく西パシラも同様の風景となっていました。ちょうど7番のトラムが来たので、西パシラも少しく車窓からの景色を楽しんでみました。建物沿いの道を縫うように走るトラムの線路のきめ細やかな敷設には感心させられます。 トラムで又、ヘルシンキ駅まで戻るのは単調なのと、時間がかかるのでパシラ駅から一駅ですが、鉄道に乗ることにしました。駅の西側、随分大規模な工事が進行中です。
調べた訳ではありませんので、解りませんが再開発であることには間違いありません。乗るともなくホームを眺めていましたら新しい近郊型電車が到着しました。行き先の表示を見てMYYRMÄKI の先に飛行機のマークがありました。何も考えずに、空港に到着すると私は、いつもFinnairのバスでヘルシンキ市内へ向かっていました。鉄道好きの私としては、少々迂闊でした。現在、MYYRMÄKIから路線はさらに伸びてヘルシンキバンター国際空港を経由して、ヘルシンキ中央駅へと続いています。ヘルシンキ駅は終着駅スタイルですから、山手線とは異なりますが、内回り、外回りでヘルシンキ郊外を結んでいます。
フィンランドに長く住む友人が、西隣のエスポー市へもさかんに地下鉄の工事が進められていて、道路は工事、工事で運転しづらいと嘆いていましたが、地下鉄は、将来的に空港までも伸びそうです。どうもパシラの再開発は、鉄道の増設も含めて、その一環のようです。全ての面で、古き良きフィンランドは、ヘルシンキからは消えて行きそうですが、一極集中と地方都市の変貌を、私の目でしっかりと見続けたいと思います。
2016-03 トラム沿線
週末、ヘルシンキでぶらりとトラムに乗りました。2日券(12€)を買っていたので、市内の市電、バス、地下鉄、鉄道は乗り放題です。乗り間違えたら、降りればよいだけですが、結構路線は複雑です。昔は、ライン3のみがTとBで市内を内回り外回りの感じでしたが、現在は、2と3が引き継ぎ、鉄道の次の駅Pasilaパシラ付近で7がABで巡回するなど乗り慣れていないとけっこう難しい。系統は、1,2,3,4,6,7,8,9,10の9路線です。町の中心部でも、何年かすると平然と線路が変わるので、これには驚きです。ただ実にきめ細やかに走っているのには感心させられます。町並みにトラムは似合います。特に古い建物が背景ですと絵になります。ヨーロッパの多くの都市がそうですが、鉄道駅を降りると駅前にはトラムが走っています。旅をしていることが実感できる風景です。同じ鉄路のつながりを感じるからでしょうか。
数年前、トラム(raitiovaunu)No 8でアラビアのショップを訪れた時は工事中でアウトレットの入り口が複雑でしたが、現在は、昔のアラビアの工場の煙突の建物の横が、ガラス張りのエントランスとなっていて煙突さえ見つければすんなり入場できます。建物にしるされたARABIAの文字と煙突を見るだけでとても懐かしさを覚えます。
現在は、イーッタラ傘下ですのでアラビアでも何でも買えますが、昔、アラビアの工場の時は、アラビアの食器がメインでしたから、知人の紹介で、内部の窯、絵付け製作現場等々を隅々まで説明してもらい、とても楽しく見て廻る事が出来たことを覚えています。帰りがけに正規の食器は当時、高くて買えないので、セカンドメイドを思い切って買いました。大学の学生寮での生活で、アラビアの食器で食事をしていると、フィンランドへ来ているという実感がわいてきたものです。その食器類は今でも健在で、新しい食器と混在で使っています。パラダイス絵柄のマグカップは、一度柄が取れて自分で修理したので使えますが、棚に飾ってあります。40年以上前のものですが、現在でもパラダイスのシリーズは、人気があって製作が続いています。時を超えて共有できる器は素敵ですね。
今回は、特に食器を買う予定もないので、またトラムに乗って、景色を楽しみながら中央駅方面へ向かいました。
2016-02-2 久々のフィンランド 3
いつもは忙しく動き回るフィンランドですが、用件が全部片づいたので週末は、ヘルシンキで過ごすことができました。ゆっくりと市内を散策するため、ホテル正面からtöölönlahtiトゥーロ入江沿いを一廻り、オペラハウスもゆっくりと見て歩き、対岸の木造3階建ての石造建築財団の横を通って、ヘルシンキ中央駅へと歩きました。駅のエリアは大幅に変化が見られます。
私は、ヘルシンキという町は、何十年ぶりに訪れても、古い建物はしっかりと残っていて、昔の旅情を思い出させてくれるとても良い町と、いつも言っていました。駅舎から正面の扉を出ると、確かにビルは昔のままに存在しています。レヴェルのフィンランドでは珍しいコルビジェの影響を受けたセンタービル、石造りのセウラフオネホテル確かにそのままです。駅舎のホームにガラスの屋根がかかっても特に違和感はありません。中央郵便局が建物だけになり、マンネルヘイム将軍像の横に現代美術館、新聞社のガラス張りビルまでは、都市の活性化のためには、仕方のないことと思っていました。でも、貨車の操車場が消え、その跡地に次々とビル群が立っています。音楽堂が完成し、次は中央図書館、事務所ビル群と駅の西側だけを見たら、昔ののどかなイメージは全くありません。東京から比べたら人口5,60万の都市の変化など微々たるものかも知れません。でも、ヘルシンキ中央駅を出発しての車窓の景色は、のどかな出発風景から、ほんのわずかですが、ビル郡を抜ける中部ヨーロッパの都市と変わらないものとなってしまいました。
今を生きる人々の生活が優先で、一時の旅情などに口を挿む資格はないのかも知れません。昔、アールトが提示したヘルシンキ中央駅一体の都市計画が、奇抜でヘルシンキ市民に賛同を得られなかった事が、思い出されます。どちらが良いというのではなく、人工的ではない空間が、より多く存在していたのは、歴史の皮肉なのでしょうか。
少しがっかりしながら、街を港に向かって歩くと、依然町並みは、古い建物をしっかりと残し存在していて、私の気持ちをまた、なごませてくれました。
2016-02 久々のフィンランド 2
プダスヤルビ町を出発して、主要道78号線を北へ70Km、雪はしんしんと降り続いています。ラヌアで休憩、この町には少しユニークな自然動物園があります。動物の生活圏を守るため、熊には熊のストレスを感じないスペース、トナカイにもトナカイに合った敷地が与えられています。見学者の立場ではなく、動物のたちの生き方を見させてもらう感じです。ですから、動物園なのにお目当ての動物が見れないこともしばしばです。 さすがに、冬は閑散なのでしょうね。スノーモービルサファリの施設が加わって衣替えしていました。
休憩をとってさらに北へ80Km有名なサンタクロース村のあるロバニエミ市へ到着です。昨年はサンタクロース村倒産かと紙面をにぎわせました。ロシアの景気の落ち込みでロシア観光客が激減したからです。幸い新しいスポンサーが表れて一難は去ったようです。これからこの町は、多くの観光客でにぎわいます。もちろんオーロラを見るためのツアー客です。特に、日本の方は本当にオーロラが好きですね。
私はいつも、この町ではホテルを取らずに、友人宅へ泊まります。町には大きな川が2つ流れていますが、さらに北極圏寄りにNorvajärviという湖があります。車で20分程の湖沿いに、彼の大きなログハウスの自宅があります。1人の時は、いつもわが家に泊まれと言ってくれる古くからの仕事付き合いも長かった友です。今は、自分の会社を弟に譲って、夏場は300Kmも北のコテージで御夫婦で生活しています。昨年は川で、合計230Kgほど鮭を釣ったそうです。フィンランド人は、釣三昧、狩三昧と大きな会社を経営していても定年となると、いとも簡単に会社を辞めて趣味の世界へ入っていきます。家族に粗大ごみ扱いされることなく、趣味の時間が、生活そのものになって生きていく余裕でしょうか。自然との関わりを大切にしてきた国民性なのでしょうか。自然に恵まれていることは確かですが、生き方は、幼い頃から培われてきたモノなのでしょうか。日本では田舎暮らしが、最近さかんに言われていますが、あえて挑戦者たる覚悟を必要としない生き方も、フィンランド人の友人を見ていると一朝一夕で出来るものではないのでしょうね。
2016-01 久々のフィンランドで感じたこと
怪我の後、約2年近いブランクのフィンランド出張でした。ヘルシンキ空港から乗り継ぎで、北のオウル市へ飛んで、翌日レンタカーで北東へまず、80Kmの移動です。仕事の忙しかった以前は、月の半分は、毎日運転したなれた道ですが、久々のドライブは、雪の遅かった北海道はまだ冬道になっていなかったので、いきなりの冬道の運転と少し緊張しました。シャーベット状の雪は滑るのですが、フィンランドのレンタカーは、スパイクタイヤなので、少し楽に走れます。
人口8千人ほどの町の郊外に取引先の工場はあります。町の中心部を一回りして、オフィスへ向かいました。近年、ログハウスの仕事は多くないので、社長とは7年ぶりくらいの再会です。合理化の進んだ工場を隅々まで案内してもらってから、工場の食堂で昼食、続いて現在進行中の大きな現場を見せてもらいました。フィンランドで最大というログハウスの建物は、学校で9800m2もあります。
フィンランドも他国と変わりなく、大都市一極集中が進んでいます。特に首都ヘルシンキ及び近郊に顕著です。ですから、田舎の町は、取り残され、人口がどんどん減っていきます。見学させてもらった学校は、 プダスヤルビPudasjärviという町で、現在全フィンランドから注目されています。注目を集めている理由は、点在する小中学校を、国道沿いの町の中心部に集め新校舎をログハウスで建設しています。三翼に分れた校舎で、それに給食センターが併設されています。児童は、バス、自家用車等で通学します。この給食センターは児童への給食はもとより、地域の老人住居、施設への配膳もこなします。
町長が、ユニークな方で老人へのコンクリート施設は、精神衛生上も良くないと、今、町の中心部にこれまたログハウスのテラスハウス(長屋)を新たに何棟も建設しています。
今日本では、過疎化が進み、地方都市では、財政難でコンパクトシティーの取り組みをさかんに言われています。土地にゆとりがある田舎でこそ、
プダスヤルビ町で始まろうとしている計画が、新たな町の行き方として参考になるのではないでしょうか。