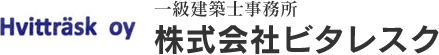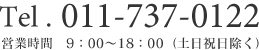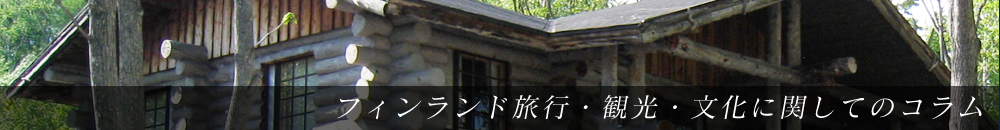HOME > コラム
2003年2月15日 土曜日 ヒーヒト・ロマ(スキー休暇)
フィンランドでは、2月下旬から3月にかけて全国を南から北へ三地域に分けて順次、スキー休暇に入ります。南のヘルシンキ地域から始まって、最後はロバニエミを中心とするラップランド地域は3月9日から14日まで。小学校から高校まで休みになるのですが、親達も年平均45日の有給休暇の一部をこのヒーヒト・ロマに合わせて家族で休暇を楽しみます。 大都市の集中しているヘルシンキを中心とする南部地域の休みの時期は、北のスキー場、ホテル、飛行機は全て予約で一杯となります。2月も下旬になりますとラップランドでも日照時間が少し長くなり、気温も厳しさが緩んで絶好のスキーシーズンとなります。 今年はフィンランドも暖冬でヘルシンキでスキーができたのは、ほんの数日程度でしたから、北に向けての家族単位の移動は多かったようです。スキー場といっても起伏の少ないフィンランドのことですから、コースは長くても1キロ弱、Tバーリフトが主流です。しかし、スキーセンターを中心にホテル、コテージが配置されて見事に景色に溶け込んでいます。コテージにはサウナと暖炉が必ずついていて、スキーで疲れた体を癒してくれます。そしてほのかな暖炉の炎は夜長の会話を一層暖かく包んでくれるのです。木の香りの中で過ごす一週間は家族にとって、心身ともにリフレッシュするよい時間なのです。
2002年9月15日 日曜日 オーロラの夜のサウナ
ヘルシンキから北へ1,200キロ、北極圏に位置するイナリというラップランドの小さな町。ここは、ラップランドの人々の中心地。フィンランド第二の湖イナリ湖から水上飛行機で進路をさらに北へ。ロシア、ノルウェー共に国境から10キロ地点の友人の地に無事着水。彼の愛犬が出迎えてくれました。今ではフィンランドでも珍しくなったスモークサウナにての歓迎。サウナ室内にあるストーブに薪を入れ、扉を少しだけ開けて静かに焚き続けるのですが、煙突がないので室内に煙が蔓延、温度が上がったところで扉を大きく開けて、煙を追い出してからサウナ室に入り、ストーブの上の石に水をかけ、湿度を上げて体感温度を上げます。体中すすだらけになるのですが、軟らかな温かさは他のサウナの比ではありません。火照った体を涼ませるために外へ出ると夜空には一面緑色のカーテン、一秒として同じ姿を見せないオーロラの営みには、時を忘れて見入ってしまいます。原生林の中のサウナそしてオーロラ、自然と共に生きる素晴らしさを知っているフィンランド人にとってサウナは、文化そのものなのです。