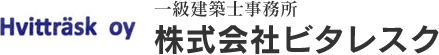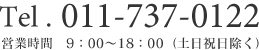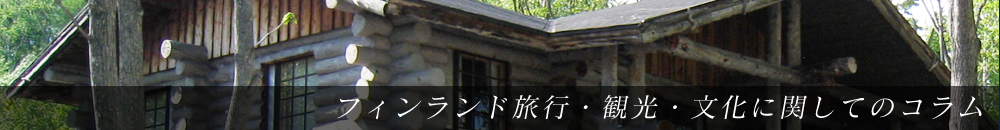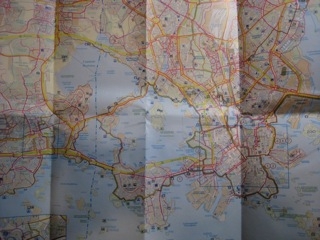HOME > コラム
2011年9月1日 木曜日 住宅街の電柱
北欧の町の住宅地を歩いていて、いつも思うことは、自然の風景と住宅に違和感がないこと、つまり景色に住宅そのものが、溶け込んでいることです。 北海道も風景だけを見ると、北欧と変わりません。特に道東へ行きますと北欧の景色そのものです。これに建物が加わると色彩というか、センスというべきか、いかにも北海道らしくなってしまいます。 もう一つ決定的に景色を悪くしている物といえば、電柱です。見苦しいコンクリートの柱が、我が物顔で道路脇を占拠して、時代遅れの文明を誇示しているようです。なんの美的センスもなく電線が張り巡らされ、さらに住宅への引き込み線となると、目を覆いたくなる醜さです。 最近、幹線道路はようやく、無電柱化が進んできました。これは美的センスより災害時等に電柱の倒壊で、救助活動や物資の輸送に支障をきたさないための措置のようです。その結果、住宅街の電線がますます醜くなっていることを、みなさんはご存知でしょうか。私は、朝の犬の散歩がてら、この光景を見ています。幹線道路から引き込んでいた電線は地中を潜って住宅街の電柱の根元へ。雨後の筍のように黒いパイプが束になって電柱を取り囲んでいます。結果、住宅街はますます醜い電線を増やしています。 写真は、フィンランド小さな町の住宅街です。ごくごく普通の景色なのですが、街路灯だけで道路脇に電柱は存在しません。住宅が極度に少ない相当田舎に行かないと電柱は見当たりません。住宅街のブロックごとに電線を引き込むボックスが設置されています。ですから、住宅を建てるときは、このボックスから電源が供給されるのです。 ヘルシンキのような都市部においては、ヨーロッパ全体もそうですが、道路の両サイドのビルの外壁からワイヤーで、街路灯を支えています。市電の集電線も同様に壁で支えています。ですから、電柱のみならず、街路灯のポールさえ少ないので、すっきりした町並みになっています。
2011年7月1日 金曜日 白夜祭(夏至祭)
久々にニセコで白夜祭(日本は、白夜にならないので正確には夏至祭でしょうか)を、行いましたのでその様子をお伝えしようと思います。昔、日本へ帰ってきてまもない頃は、自宅でベランダに白樺の枝を飾り友人を集めて、夏の夜長を楽しんだものです。でも、お互い家族が出来て、日常の生活に追われるようになり、そのような行事が、長らく途絶えていましたが、今年は、あまり明るい話題がありませんでしたし、ニセコのコテージ竣工20周年ということもありまして旧友に声をかけました。 夏至の週末、6月25日にニセコのコテージ集まってもらい、フィンランドと同じく、入り口の門近くに大きなフィンランド国旗を掲げ、ベランダには、白樺の枝を飾り、屋外のサウナ小屋には、夏至のサウナを楽しめるように火を入れて皆の到着を待ちました。バーベキュー小屋に炭をセットして、スモーク小屋へは、肉の塊、魚を入れて、焚き口から薪をくべてスモークのスタートです。焚き口のストーブの上は、数時間火を絶やさないので、かなり高温なります。そこで今回は、耐火レンガを水平に敷いて熱が逃げないように、スチールでカバーを作って、簡易ピザ釜も用意しました。 続々と懐かしい友人が集まってきました。ひとしきり昔話に花が咲いていたのだと思います。私は、夜のメインイヴェントのユハンヌスコッコの準備です。フィンランドでは、各都市でこの行事が行われます。ヘルシンキでは、セウラサーリという屋外博物館のある島で、毎年行われます。ユハンヌスコッコ(白夜の篝火)は、そもそもは、古い船を数隻立てて燃やしていたそうです。セウラサーリでは、大きく積み上げられた木々に、沖からボートで新婚カップルが来て、点火といった演出がされたりします。 ニセコでは、裏の畑にセットしました。中央に1本白樺の木を倒れないように埋め込み廻りに3本白樺の乾燥した木を縄で縛りつけ芯を作りました。暖炉に使う薪を三方に井形に組んで1メートルより高く積み上げました。隙間には笹の枯れ葉を詰めて燃えやすくして準備万端です。 バーベキュー、ピザ、皆様が持ち寄ってくれた豊富な飲み物で、食も充分満たされた夜8時、いよいよユハンヌスコッコへの点火です。裏へ移動した音響装置からフィンランド国歌MAAMMEの演奏終了と同時に着火です。三方から静かに炎が上がり、やがて一体となって見事に炎が天に向かうように大きくなっていきました。フィンランディア、カレリア組曲とシベリウスの音楽は裏山の森へと響き渡ります。約1時間全員が炎を見つめていました。篝火が小さくなって、暗さをました天空では、見事な天の川が夜空をうめていました。
2011年6月1日 水曜日 ユハンヌス(夏至)のサウナ
今年の夏至は、6月22日ですから、フィンランドは、週末の25日が祝日です。この頃になると、夏休みをとり始める会社も多いので、ヘルシンキ市内は、閑散とします。日本のお盆を思い浮かべていただくと理解しやすいかもしれません。6月24日の金曜日から、一斉にみんな故郷を目指します。普段あまりおきない国道の渋滞が始まります。特にこの季節、太陽の位置が高いので、直射日光ををまともに浴びて、車内の温度はどんどん上昇します。でも、果てしなく続く森林の緑と、左右に絶え間なく現れる光り輝く湖面を眺めていると、いらいらは募りません。一年で一番いい季節の到来です。故郷へ帰って過ごす夜は、やはり夏至のサウナです。 今回は、サウナを少し詳しく紹介します。フィンランドでも今は、電気ストーブのサウナが一般的です。シーズヒーターが充分に高温になって覆うサウナ用の石(香花石)が熱くなったら、桶に入った水をスクープで石に2、3杯かけます。瞬く間に蒸気となってサウナ室を熱気が走ります。この熱さで体を暖めるのが、本当のサウナの入り方です。日本の町場のサウナのように、室内を100度にも上げて入る方法は、決して体に良いとは言えません。せいぜい、室温が70度まで上がったら充分サウナを楽しめます。水を何度かかけて、体がほてってきたら、白樺の小枝を束ねたビヒタで全身をたたきます。体に程よい刺激と、白樺の香りがサウナ室に充満します。これがサウナの醍醐味です。 今でも、フィランドの田舎へ行くと薪焚きのサウナストーブを使用している家庭が多くあります。薪ストーブの体感温度は、電気に比べて柔らかく、サウナ嫌いという日本人でも、多くの人がサウナ好きに変わります。薪焚きのサウナストーブは、取り扱いがいたって簡単で、暖炉用の薪でなくても、建築端材でも充分燃やせます。夏場ですと、30分位でサウナに入れる温度になります。薪のサウナのもう一つ良いところは、電気設備の容量アップとか心配がいりません。ですから、土地の広い北海道、特に農家の方などへ、離れのサウナ小屋の新設をお勧めします。風景では、北海道とフィンランド、とても似ています。これに、サウナライフが加わると豊かな北欧の人々の生活に、北海道も一歩近づくのではないでしょうか。
2011年4月1日 金曜日 古くて趣のある建築散歩6
大雪、寒波と厳しい冬だったフィンランドもようやく春の兆しが見え始めているようです。4月に入って、最高気温が10度を越す日も出てきました。 今回は、何十年も昔、私がヘルシンキ大学の学生時代から気になっていた建物を紹介します。市電トラムの市内を8の字で回っている3Tあるいは、3Bに乗って南港近くのLaivurinkatu(ライブリン通り)とTehtaankatu(テヘターン通り)が交差して、市電が大きくカーブするところ、停留所名はeiran sairaala で降車します。角に赤茶けた瓦の屋根と黄土色の厚い壁の建物が見えます。建物の名前はエイラホスピタルです。1904年から1905年にラルス・スンクの設計によって建てられた病院です。敷地に高低差があるので、建物は大きなL字型のプランで両面道路にそって建てられていて、基礎部分が石積みで半地下構造の3階建て、その上は屋根裏部屋になっています。庭に面する側は1階の壁半分が石積み上部がレンガ、しっくいの4階建ての構成になっています。庭側L型の廊下中央に大きなき階段、同じく庭側のつき出した尖塔は、らせん階段になっています。 このエイラホスピタルは、コラム51、56で紹介した建物と同じ建築家です。作曲家シベリウスの、ヘルシンキから北へ30Km Järvenpääヤルベンパーの山荘アイノラも、シベリウスの友人である彼の設計です。 交通手段があまり発達していなかったこの時期に、まして、建築現場も、現在では想像もつかないほど、非機械化の人力による建設が行われていたとおもいます。時間を要したその時代に、ヘルシンキ市内のみならず近郊へ出かけて次々と大きな仕事をこなしているのですから驚く限りです。 電話局の建物が1903-05年、アイノラが1903-04年、同時期の仕事です。これらの建物に共通して言えることは、この時代の主流である、ナショナルロマンティシズムを端的に表現している建物だということです。尖塔、石積みのアーチ玄関、バルコニー、ガーデンウォール、建物を見ているだけで古き良き時代へ入っていけそうです。
2011年3月1日 火曜日 ジョギング、自転車道
今年のフィンランドは、大雪だけでなく、2月にはかなり厳しい寒さも続いていたみたいで、オウル近く北緯65度の取引先からのメールでは、連日マイナス30度を下回る日が続いていた様です。でも3月に入りますと日の出が目に見えて早くなってきます。朝、普通に起きて真っ暗な空が、日本と変わらなくなってきます。春とまではいかなくても、朝の散歩も日差しを感じることができます。フィンランドは実に良く、歩道、自転車道が、整備されています。日本のように歩道を自転車が歩行者を無視して走るような危険なことはありません。完全な自転車専用道路は、まだまだ少ないのですが、幅の広い併設の歩道、自転車道は、ヘルシンキだけを例にとってみましても、現時点で1200kmもあります。サイクリング、ジョギングコースとして、中心部はルートが限られていますが、郊外では普通に幹線道路と交差するところは、基本的にアンダーパス等で、立体になるようにコース作りがされています。これは、冬においても除雪が完璧になされています。さすがに12月大雪の時は、追いついていませんでしたが。 ヘルシンキ近郊のサイクリング、ジョギングコース等を示したアウトドア専用地図も、ヘルシンキ市旅行案内所でもらえます。地図を広げて驚くのはコースが全市にきめ細やかに整備されていることです。この地図には、もちろん冬のノルディックスキーのコースも記されています。今日本でも少しずつ浸透してきた、ノルディックウォークにも最適です。今月は、少し寒い風を感じても、4月からは、本格的なアウトドアシーズンです。もし春からフィンランドを訪れる予定のある方は、ジョギング、あるいは、自転車を借りてのサイクリングをお勧めします。観光バスからの視点とは異なるフィンランドの姿が見えてくると思います。フィンランドの教育レベルが、世界でトップだとよく取り上げられますが、これは、ぶれずに長いスパンで、教育を考えた成果だと思います。フィンランド人は、そもそも運動好きですが、ジョギング、サイクリングロードも、行政の仕事という押し付けではなく、使う人の立場にたって造られてきたから、結果としてこれだけ整備されたのだと思います。
2011年2月1日 火曜日 列車の旅
今冬のフィンランド、昨年12月からの大雪が続いているみたいです。私は、メーカーとの打ち合わせ、いつもはレンタカーで移動するのですが、フィンランド航空のストで、本来なら夕方にヘルシンキ空港へ到着だったのですが、他社の便を使っての到着、翌日午前3時半、しかもストのため旅行バッグは飛行機から出てきません。あきらめてホテル向かいましたが、ヘルシンキ市内は大雪でした。仮眠の後、西へ120Kmほどの車の移動をあきらめ、中央駅へ向かいました。カードによる自動の切符購入はもちろんできるのですが、手間取ると後の人に悪いと思って、ホール左手の切符売り場へ、順番待ちの切符をとって番号の表示を待ちます。日本では、銀行等今ではごく普通に順番待ちの切符を取りますが、フィンランドでは、私が学生生活を送っていました40年近く前からデパート、スーパーの肉売り場等で既に採用されていました。 目的地、希望乗車時刻を伝え切符を受け取り列車のホームへ。近郊列車は、電車車両が多いのですが、都市間列車は、電気機関車で引かれる客車車両が多いようです。今では、厳つい車両が姿を消してスマートな2階建ての車両が増えました。久々の列車の旅なので隅々見て回りました。 キッズルームが備えてあったり、携帯電話を使用するコーナーまで設置されていました。その横のスペースは、車内販売のカートのためのエレベーターでした。感心しながら表示板を見ると、時速140Kmで揺れも少ない快適な乗り心地、ヨーロッパ標準軌(日本の新幹線も同じ)1435mmより広い1524mmの広軌鉄道はさすがです。途中乗換駅で列車を換えましたが、同じく快適でした。降車駅が近づいたところでおばあさんに話しかけられました。「日本で議員になったフィンランド人を知っているか。」どうやら親戚の方だそうです。旅の会話も楽しみながら目的地に到着。窓メーカー(ドムス)の社長はホームへ迎えに来てくれていて、スーツケースが受け取れずに、着たきりの薄着の私の姿を見て、吹き出しました。
2011年1月1日 土曜日 ヘルシンキ地下街
新年おめでとうございます。コラムを読んでくださる皆様へ今年こそ、よい年であることを切に望みたいと思います。 昨年12月は、ヘルシンキ大雪で、街を歩くのも大変な状態でした。それで極力、地上を歩かずに済む方法を考えたのですが、 新しいショッピングモールKAMPPI(コラム30)とヘルシンキ中央駅(コラム3)の通路は知っていたのですが、 以前のショッピングモールFORMと、ストックマンデパート(コラム46)の地下までが、すべて一体になっているのには、 少々驚かされました。普通、新しい地区ができると、古いところは活気をなくするものですが、全てをつなぐことによって、 活気を取り戻しているのです。岩盤の地層ですから、掘削は難しくても構造的には可能という利点もあるのですが、 繋ぎ方が実にうまいのです。ヨーロッパの諸都市同様ヘルシンキは、道路に面して建物が並びブロックごとに中庭が 存在するのですが、このスペースを利用して、高低差を解消しているのです。しかも中庭には、ガラスの屋根をかけ、 こちら側も商業スペースとして新たな活用をしているのです。岩盤ですからトンネルの一部は壁はむき出し、 地下駐車場(一部は防空壕施設)もそのまま通路と利用して、縦横無尽とまではいきませんが、十分に中心部を行き来できる のです。寒い北国の知恵を今更学んだ気がしました。
2010年12月1日 水曜日 ヘルシンキ 古くて趣のある建築散歩 5
クリスマスが近づくとヘルシンキで最も活気づく通りは、Aleksanterinkatuアレクサンテリン通りです。フィンランド最大のデパートも正面入り口はこの通りに面しています。クリスマスのイルミネーションで飾られ、一年で一番暗いこの季節、この通りは輝きを増します。 デパートからさらに港よりに進んで行くと左手に、明らかに他の建物と異なった外観のビルが見えてきます。Selim Lundqvistの設計による1898年着工、1900年完成の商業ビルです。通りを隔てて対峙するサーリネンのビルのように、この時代、フィンランドの叙事詩カレヴァラを題材としたナショナルロマンチシズムの石造りの重厚な建物が数多く建てられた中心部に、鉄とガラスとレンガの建物は、かなり人目を引いたに違いありません。 地下1階地上4階にペントハウスの5階建て、アレクサンテリン通り13番地なのでアレクシ13と呼ばれ、現在は、デパートとなっています。もちろん内部はエスカレーター等が設置されていますが、建設当時の正面入り口は、吹き抜けになっていて、各階の天井はとても高く、奥には、なだらかな半円の螺旋階段で各階がつながっていました。現在とはかなり異なる内部空間を有していたと思います。
2010年11月1日 月曜日 アラビアARABIA 食器Valencia
最もアラビアらしい食器を一つあげるとしたら、私は迷わずバレンシアと答えます。同じブルーでも、繊細なロイヤルコペンハーゲンとは異なるのですが、コバルトブルーの力強いタッチは見ているだけで気持ちを弾ませてくれます。 昔、イタリアのブリンディジからフェリーでギリシァへわたった時、アドリア海を眺めていて、アドリアンブルーの美しさを知りました。同様にスペインの赤茶けた大地とコバルト色の空のコントラストも目に焼き付いています。日本の藍とは異なった大陸の色を感じました。 1960年Ulla・procopeウッラ・プロコペは、コバルトブルーの全て手書きのバレンシアを発表しました。コーヒーカップもソーサーも全て手作業です。工場で見学していますと、職人がものすごい早さで食器に模様を付けていきます。裏には、当時アラビア、ヴァルツィラの文字が書かれていました。 造船大国のフィンランドは、砕氷船、大型フェリー、客船で、当時ヴァルツィラ、バルメットが、二大メーカーでした。アラビアは、ヴァルツィラの傘下で、便器等の衛生器具も生産していましたから、ヴァルツィラは、客船のエンジンから、客室の施錠システム、便器、食器まで自前で揃えていたことになります。ちなみに日本のINAXは、当時衛生器具でアラビアと提携していました。 時代は変わって、造船業界は、吸収合併を繰り返してノルウィーのクバナーマサヤーズの傘下に入ってしまいます。同様にアラビアは、イイッタラのグループに取り込まれ、私の愛したバレンシアも2003年生産を終了します。 何でも、手書き職人の高齢化ということですが、企業の合併による合理化 です。でも、これだけは残してほしかった思いがします。 2003年以降、私はフィンランド出張の折に、地方のショップに残っているバレンシアを買い求め、万が一破損しても日常生活で使い続けられる量を確保しました。ですから、今も秋の夜長を、バレンシアのカップでコーヒーを飲みながら、友と語り合う時間を楽しめています。
2010年10月1日 金曜日 アラビアARABIA 食器Paratiisi
私が、ヘルシンキ大学生のころ、一番最初に買った食器が、モーニングカップに使用していたアラビア、パラダイスのティーカップ。デザイン立国のフィンランドで生活するのですから、まして建築を学ぶものとして、デザインにはこだわりたかったのです。もちろん貧乏留学生の私は、ヘルシンキ在住の日本人に、アラビアの工場へ連れて行ってもらい、工場を見学、職人の説明を受け、工場のショップで自炊するための最低限の食器を、セカンドメイドでそろえました。 1969年デザインのパラダイスBirger・Kaipiainenカイピアイネンは、フィンランド人にとって、建築界のアールヴァー・アールト同様、知らない人がいないくらい有名で、セラミックのプリンスと呼ばれていました。1977年には、プロフェッサーの称号を受けています。 この、パラダイスシリーズは、日本では、作曲家の都倉俊一氏が、当時お父様が、スエーデン大使であったことも起因していると思うのですが、1974年女優の大信田礼子との結婚の引き出物に使われて有名になったと思います。 フィンランドにおいては、もちろん長らく愛されていたのですが、毎年新しいデザインが、店頭に並びますので、存在価値は薄れていきました。ところが、大統領公邸が、建築界の巨匠アールトと並ぶライリ&レイマ・ピエティラの設計によって1993年秋、MÄNTYNIENIに完成しました。そこの大統領のプライベートダイニングに全面的にパラダイスシリーズが採用されました。カイピアイネンは、1988年にすでに他界していましたが、建築雑誌、女性誌等でパラダイスが取り上げられ、再び、フィンランド人に脚光を浴びたのです。