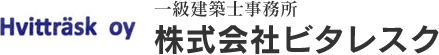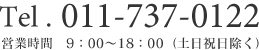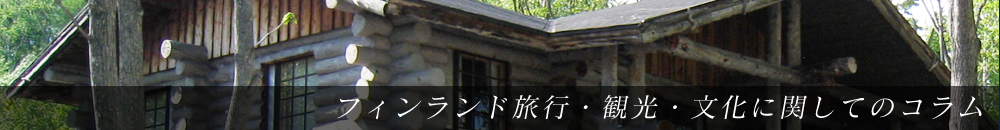HOME > コラム
2007年3月9日 金曜日 ノルディック王国北欧
2月22日から札幌で行われていたノルディックスキー世界大会。残念ながら、冬季オリンピックと並ぶ世界大会なのに、札幌ではあまり盛り上がらず、入場予定人数を大きくしたまわり、悔いを残す大会となってしまった。私は、ノルディック競技をしばしば北欧で見ているので、観客数と熱気の差にがく然としてしまう。ノルディックスキー人口の少なさ、底辺というか一般競技人口を増やす事なく強化選手の育成のみを行ない、大会のみを求めるアンバランス。巨額の出費を伴いながら、折角のチャンスを生かせなかったノルディック世界大会。しかし、収穫もあったと思う。11日間、競技場、交通機関案内等で、活躍されたボランティアの人々、動員かもしれないけれど、会場につめかけた小中学生。彼らには、きっと自分が参加した、自分たちが見つめた大会として心に残ったと思う。札幌ドームを開会式、競技に使ったという新しい発想も札幌大会を世界へアピールできたと思う。 距離競技会場の白旗山にテントを張って寝泊まりしていたノルウェーの応援団、いつも大きな国旗を持って世界を転戦しているフィンランドの応援団、年金生活をこのような形で楽しめる北欧の人々、国の豊さは、このような事にも現れるのではないだろうか。 我が、フィンランドは、1972年の冬季札幌オリンピックが、最悪の成績だったという雪辱をみごと果たした。実力はトップでありながら、世界大会で勝てなかった無冠の帝王マンニネンは、距離、複合で2つの涙の金メダル、女子も健闘して2つの金メダル、総合メダル数では、ノルウェーに劣ったけれど、金メダル数は、同数の4個、フィンランド人にとっては、札幌はすばらしい大会になったに違いない。札幌で競技が行なわれていながら、ヨーロッパでは実況中継がなされ、地元札幌は、実況無し、唯一の銅メダル、ジャンプ団体競技でさえ時間遅れの録画放映とは情けない。今回の大会を糧として冬を楽しむ生活を、若い世代はもっと北欧から学んで欲しい。
2007年2月9日 金曜日 ガラスパレス
ヘルシンキ中央駅近くのホテルバークナ、ソコスデパートの建物とマンネルヘイム大通りに対峙して建っている低層二階建ての建物。前にも中心部の再開発で触れた、この建物をもう少し紹介したい。1935年完成のこの建物は、3人の建築学科の学生の設計で、名前は、ヴィリヨ レヴェル(1910-1964)、ヘイモ リーヒマキ、ニロ コッコ。 国立博物館、中央駅の設計者、サーリネン達同様、学生時代から活躍していたのだからすごい時代だ。サーリネンが、古典主義的建築であったのに対して、このガラスパレスは、ヘルシンキに建てられた最初の機能主義建築と言われている。ヘルシンキ南港そばに建つ1952年完成のパレスホテル(ケイヨ ペタヤとの共同設計)も同様、コルビジェの影響を強く感じる。この時代、次々とすばらしい建築家が、この北欧の小さな国で生まれたものだと感心させられてしまう。北欧合理主義のデザインの原点は、この時代から芽生えていたのかもしれない。 このガラスパレスは私が、学生時代を過ごしていた30年前からでさえも、大きく変る事はなかった。もちろん入居している店はいくつも変わっているのだが、映画館、レストラン、喫茶店、書店、花屋と店構えは同じようなもので、建物の雰囲気が異なってしまうという変化は感じられない。フィンランドの景気のよさもあって中心部では、かなりの建築ラッシュで、次々と再開発が行われているが、このガラスパレスは、きっと建物の寿命が来るまで、生き続けるに違いない。 ヘルシンキを訪れた人は、少々古びたこの建物をきっと見ているに違いない。古いものだから残すのではなく、フィンランドの決して長いとは言えない歴史の中で、町と共に歩んできた年月を語るもの、低層であるがゆえにかもし出せる存在感、そんなことを考えながらこの通りを歩くとヘルシンキは、実にスケールが人間的な、都市という人工空間をあまり感じさせない町である。
2006年12月4日 月曜日 クリスマスのフィンランド
クリスマスを控えた週、18日に急遽フィンランドへ出張。ヘルシンキから北へ500kmのオウル市まで、国内線に乗り換え飛行場からレンタカーでオウル市内のホテルで一泊。ヘルシンキ空港でレンタカーの予約を済ませていたので、到着後キーを受け取り駐車場へ行くと、車内はすでに暖たたかい。北国ならではの担当者の心遣いが外気と対照的でありがたい。 翌日さらに北へ140Km、打ち合せのため車を走らせて行く。暖冬の影響で国道に雪はなく快適なドライブ、朝10時近くになってようやく日の出、この日はマイナス16度、内陸部にしては決して厳しい寒さではない。木々の白い輝きが、朝日の色と溶け合って美しい景色をかもしだしている。ついつい車を止めてシャッターを切りたくなる。この地での打ち合せを、無事に終えて同じ道を引き返す。午後1時半同じ景色の夕暮れが始まっていた。 ヘルシンキへ戻ると夜から朝にかけてみぞれ、町を白くするほどのものではなかった。クリスマスのイルミネーションが、いつもの景色とは違う。週末を控えどの店も買い物客でにぎわっている。フィンランド最大のデパート、ストックマンの恒例ウィンドゥのクリスマスデコレーションには、子供たちが集まっている。どうやら大規模な改修工事の最中で少々人の流れが悪くなっている。にぎやかな商店街を抜けて港へ歩いていくと、ヘルシンキ南港は、例年の氷に覆われた景色ではなく水面を見せていた。
2006年11月4日 土曜日 フィンランドの住宅 2
フィンランド人の住宅に対する考えかたがいかにしっかりしているか、まじめに取り組んでいるかを(自分の家なのだから当たり前といえばそうなのだが、)各段階で紹介したい。まずは、基礎工事の段階から順を追って説明していこうと思う。同じ寒冷地と言われる北海道は、基礎の深さを凍結深度で決める。札幌は60cmという具合に、しかし、寒波が来るとマイナス40度にも達するこの地では、凍結深度まで掘るという考え方ではなく、基礎の地盤を、水分の少ない山砂のような置き換え土にして、基礎外部に断熱材を張り巡らせる。もちろんさらに、スカートのように断熱材を外部に敷き込む。 でも、一番大事なのは水分を基礎廻りに侵入させない事。どこの建築中の家を見ても、外部四隅にプラスチックのマンホールが飛び出している。これは、各面の住宅外部の基礎下に、暗渠が張り巡らされていて、基礎廻りの水は、このマンホールへと導かれている。さらに、当たり前なのだが、雨水の処理。基礎廻りに雨水を侵入させる前に取り除く事が最善なのである。北海道では、冬の雪による破損から、あまり使われない雨樋が、北欧では必ず設置されている。肉厚のスチールに、メッキ処理されたフッ素樹脂コーティングの雨樋は、凍ったぐらいでは、壊れるよなしろものではない。雨樋からの雨水は、当然暗渠とは、別系統の排水管を通って、マンホールへとつながっている。雨水と、暗渠の水、この二つの系統の水が、例外なく確実に処理されているという事は、住宅建設に際して当然行なわなければならない事と記されているからである。もちろん公の機関からの指針である。 本来、北海道の住宅のあり方を示して欲しい機関が、スカート断熱をする事によって基礎を浅くできるという程度の、北欧視察の誤った発想は、未だ北海道は、北欧の住宅レベルに至っていない証なのだ。前にも書いたように、今更私は、北欧の人々の住宅に対するまじめな取り組みに感嘆させられている。
2006年10月4日 水曜日 フィンランドの住宅 1
フィンランド人ほど自分で住宅を建てることを普通と考えている人々は、いないのではないだろうか。しかもその住宅のレベルは素人の域ではない。ヘルシンキ等、都市部は別としても、地方の住宅地のおおよその面積は800-1000m2、土地代は、日本なら山林を買うレベルの金額と考えていただきたい。自分で建てるという事は、建設費を大幅に圧縮出来るから当然設備など住宅の質は良くなる。 最近、日本でも住宅部材のきめ細かな販売が増えてきているが、フィンランドは昔から当たり前のように専門店が全国各地に展開されている。電気配線のように専門職でなければ許可されない設備もあるが、ほとんど自分での施工が許されている。日本の確認申請に当たる図面等は、建築士に依頼するのが、一般的である。日本のように確認申請のための図面ではなく、施工図を兼用しているようなきめ細やかな図面で、自分の家を建てようとしているプロでない人間にも理解しやすいように書かれている。施工に当たっては、もちろん、作業を細分化する事は可能で、基礎を専門家に頼むとか、壁を外注、屋根のトラスをメーカーにオーダーするとか、自分の力量にあった作業が可能である。機械をリースしてきて全て、自分で仕上げる人も、決して少数派ではない。 私は、フィンランドを訪れるとき、しばしば建築中の家を見つけると、現場へお邪魔して話を聞かせてもらうのだが、とても素人と会話しているとは思えない知識を持っているので、つい職人と話をしている錯覚に陥るくらい、みんなよく勉強している。叉、そのための書籍も豊富で、技術指導もしっかりしている。ただ、住宅を建てようと思った家族は、祝祭日、週末と、一カ月の夏休み、勤めを終えた毎夜を全て、費やす事になる。
2006年9月4日 月曜日 ヘルシンキ中央郵便局
ヘルシンキ中央駅近くに建つヘルシンキ中央郵便局は、駅の完成より30年ほど遅い1935年の冬に着工、1938年6月竣工。ヨルマ・ヤルビ、エリックリンドースの設計による建物。駅の扉が重厚な木製に対してフレームがスチールのガラス扉、石の重厚建築からスチール、ガラスの近代モダン建築の始まりだろうか。共に大きな扉は、体当たりしないと開かないのではと思うほどだ。現在はどちらも人を関知すると自動的に開くようになっている。重い二重の扉を抜けると大きなホール、銀行のようなカウンターが奥まで続いていて、手紙、小包等に番号で別れている。案内カウンターで、何番がよいか教えてもらえる。切手は切手専用のブースがあってそこで買う。30年前は、そんな時間の動きの、のどかな時代だった。数字の難しいフィンランド語の勉強に幾種類もの切手を買って実践した学生時代を、思い出しながら。現在、ホールはそのまま郵便博物館になっている、ホールを抜け階下に下りると、現在の郵便局がある。再開発された駅周辺とここがフラットになっている。決して有効な活用とは言い難いが、歴史を刻む証が、市中に充分に存在する事は、住む人はもちろん、再度訪れた人々に対しても違和感のない安らぎをあたえてくれる。独立100年を経ない小国が、通信、教育で世界のトップとなる一面のような気がする。 中身はどうであれ、一つ覚えの郵政民営化、仕事は全て中途半端で、大統領気取りで外遊三昧、7日からフィンランドを訪れる小泉首相あなたにこの国の素晴らしさをみて欲しい。全く期待はしていないけれど。
2006年8月4日 金曜日 コラム再開 フィンランド
フィンランドと関わって35年、私の過ごした学生時代は、もちろん飛行機の直行便なぞなく、横浜港から船に乗ってナホトカへ、当時のソ連邦をシベリア鉄道に揺られてヘルシンキ駅への長旅。フィンランドという国自体一部の専門分野の人を除いて、あまり日本人には興味を持たれる存在ではなかった。現在、携帯電話のノキアはもちろんの事、教育分野では、世界のトップクラスの学力で注目を集めている。 そんな中で映画の「カモメ食堂」が、年齢層を問わず人気を博している。東京で評判という新聞の記事、でもどうせマイナーな映画だろうからすぐ終わってしまうだろうと、札幌で上映が決まると5月中旬すぐ女房と観に行った。若い人が多いのにまず驚いた。個性派ぞろいの俳優、のどかな風景、思いやりのある人間関係、古き良き時代のフィンランドが映っている。 もちろん、現在でも田舎へ旅すると期待は裏切られないと思う。若い人達を意識してか、町外れの食堂にしては、ブランドの食器等おかしいけれど解りやすい。これも新聞の記事だが、俳優達が撮影を終えて、フィンランドびいきになったというから、年齢層を超えてフィンランドは受けているのかもしれない。少し意地悪な見方をすると、やはり今の日本は、病んでいるのだろうか。テンポの速い歌が続くと時代遅れのようなスローテンポの曲が流行ったりするので、世の中は単純なのかもしれないけれど。最近はスローライフが、さかんに取り上げられている。まさに、この映画はスローライフそのものである。各分野で世界の先端を行っているフィンランドがスローライフの国なのだろうか。ヨーロッパの北の果て、国民性は、そもそも素朴で決して都会的ではない。私は、35年を振り返って、長らく仕事を通して関わってきた国、今さらながらまじめな国民性に感嘆している。北海道に住んで、この大地を彼らのように生きたい。そんなフィンランドに対する気持ちをまた綴っていこうと思う。
2006年2月4日 土曜日 朝市 マーケット広場
寒波で厳しい寒さにみまわれたフィンランド。現在は、平年並の気温にもどっているようだ。2月も下旬になると太陽の明るさを感じ取れるようになる。明るさに加えて、日差しの温かさもようやく体に伝わってくる。冬場の太陽は、僅かの日照時間に加えて、ぼんやりと光っているだけで温もりを享受できないのでたまったものではない。 南港そばのヘルシンキで一番大きなマーケット広場も、この季節になるとだんだん活気を帯びてくる。依然港は氷に覆われていて、大型船舶以外の航行は不可能なので、小舟による魚のマーケットはもう少し先になる。鮮やかな春色の果物も、テントを取り払ってエスプラナーデ通りに溶け込む花市を見るのも、もう少しお預けだ。私の学生時代は、新鮮なものを求めてよく買い物に行ったけれど、市内いたる所にスーパーマーケットがある現在も、かわらずにぎわいを見せている。もちろん観光客の姿も目立つのだけれど、ヨーロッパの他の都市同様、町で確固たる地位を築いているように思われる。都市化が進む現象はどこの国でも同じなのだか、都市としての歴史の違いなのだろうか。 太陽が出始めると、散歩好きのフィンランドの人々は、こぞって外にでる。冬の便利なこともある。湖の多いこの国は、湖岸を大きく回って目的地に行かなければならなが、氷が近道を作ってくれる。対岸を最短距離で渡ることが出来るのだ。人だけではない。車道も誕生する。JÄÄTIEの看板 まさに氷の道だ。
2006年1月4日 水曜日 砕氷船
今年のフィンランドは、どちらかというと暖冬の穏やかな新年でしたが、今寒波が訪れている。北極圏ではマイナス30度、ヘルシンキでもマイナス20度近くまで冷え込んでいる。当然海は凍りつく。ヘルシンキ、ストックホルムを毎夕出発する大型フェリーも氷を砕きながら進路を確保している。当然砕氷能力を持っているが、本格的な海の結氷となると砕氷船のお出ましだ。夏と変わらぬ輸出入の経済活動を維持するために、航路の確保は、国の重要な任務である。造船大国フィンランドは、原子力砕氷船を除く、通常型砕氷船のシェアーはもちろん世界で一番である。 随分前に退いた砕氷船SAMPO(3450T)は、北のケミ市で、観光砕氷船として極寒の氷海を体験できる。網走の流氷観光船のレベルではない。今、サハリンの石油、ガス採掘が、さかんに行われているが、ここで活躍しているロシアの砕氷船も当然フィンランドの造船所で進水している。未だ現役のURHO(戦後の大統領の名前、SISU(フィンランド魂)砕氷船の名前が重要性を物語っているように思える。現在は、新鋭艦OTSO級の2隻が、主流になってきているが、船体の色はフィンランド国旗の白とブルー、船首にはフィンランドの紋章が、描かれている。夏は、海軍の管理下に係留されているだけだが、冬は活躍の場を北海にまで広げる。 少し飛躍かもしれないが、原子力航空母艦で世界の海を威圧して経済活動を有利にする国より、自然環境を技術で克服して経済活動を行なうこの国を、私は、ずうっとまっとうだと思う。
2005年12月4日 日曜日 サンタ村より最新情報
サンタ村のある北極圏入り口ではクリスマスのツーリストで大賑わいの季節を迎えています。<br>イギリス、フランス、イタリア、スペインなどからの直行便が続々と到着し空港、市内ホテルは一杯の状態です。家族連れのこうしたヨーロッパからのチャーター便はクリスマスシーズンの今年は200便前後が予定されておりその半数は既に到着しています。今週から来週にかけてがそのピークとなり、トナカイそり、ハスキーそり、スノーモービルのツアーも24時間体制の状況のようです。<br><br>さて、サンタ村ではやはり人気の的はサンタさん。サンタと一緒に写真を撮ったり、お話したり、1時間以上の待ち時間もみなさんじっとがまんしてサンタに会えるその瞬間をとても楽しまれているようです。<br>特筆すべきは、大人のサンタさんに対する反応です。日本人の方々は本当にサンタさんに会うのを子供さん以上に楽しみにされているようです。割としらっとしているヨーロッパの大人の人達より本当にその場のその瞬間を大切にかつ楽しまれているという印象があります。これはすばらしいことでは無いでしょうか。 今現在、サンタ村の中庭では日本のデパートのアレンジによる子供たちから送られたオーナメント2000枚が5mサイズの2本のツリーに飾り付けされています。日本の子供たちの夢や希望がたくさん書かれたオーナメント、本当に平和なクリスマスであってほしいと願わずにいられません。<br>このところ晴れている夜はほぼオーロラも見えています。ただお天気次第というのがつらいところですね。<br>今日の気温はマイナス15度。本格的な冬になりました。が、1週間後の冬至を過ぎるとまたぐんぐんと日が長くなりあっという間にまぶしい春の日差しになります。それまでのしばらくは薄紫色に染まる街に美しく飾り付けされたツリーやデコレーションを楽しみながらクリスマスシーズンを心穏やかに過ごしたいものです。 寄稿 kyoko.saito-simola@pp.inet.fi<br>日本人観光客のためのヘルプデスク