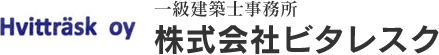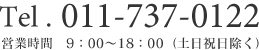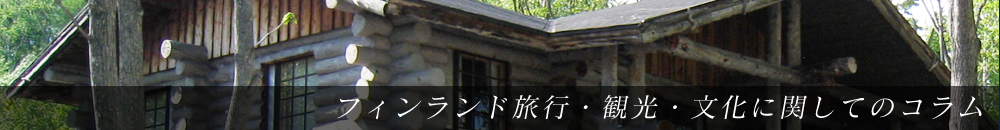HOME > コラム
2010年9月1日 水曜日 イイッタラIittalaガラス 2
1881年創業、イイッタラガラスは、ヘルシンキから北へ130Kmの小さなイイッタラ村からはじまりました。1946年からここに勤めたデザイナーのタピオ・ウィルッカラ及びティモ・サルパネヴァによって北欧デザインの黄金期を、1950から60年代に迎えます。ちなみにイイッタラの赤丸の中に白抜きのiのロゴマークは、1956年ティモ・サルパネヴァによってデザインされました。 タピオ・ウィルッカラによる1952年のtapioタピオシリーズは飲み物用に数種のサイズがあるのですが、わたしは、日本酒を冷やで飲みたくなるようなデザインの食後酒用グラス、このサイズが好きです。また、1972年のgaissa ガイッサは、氷入れとともに、ウィスキーのロックグラスとして、私は長く愛用しています。 ティモ・サルパネヴァ1966年のキャンドルスタンドFestivoは、中間の節1個高さ80mmから節8個の315mまであります。球形のローソクをのせて炎をともすと夢が広がる感じです。この球形のローソク以前は、数多くの色があったのですが、最近は白と赤以外、町中では見つけることができません。 アルバー・アールトデザインの花瓶kokoelmaも、イイッタラを最も思い起こさせる品の一つといえるかもしれません。最近は、同じデザインで小さなキャンドルスタンド等高さ30mmのシリーズから、600mmの大きな花瓶まで数多くショウウィンドゥを飾っています。 1987年陶器のアラビアのガラス部門としていたヌータヤルヴィを傘下に収め、続いてアラビアさらにステンレス食器のハックマンに加わりトータルテーブルウエアーの大きなグループになってロゴをiに統一しました。 私にとっては、シンプルなiのロゴはグラスだけのイイッタラでいてほしかった思いが強いのです。アラビアの食器にiのマークは似合わないと思っているのは、私だけでしょうか
2010年8月1日 日曜日 イイッタラiittalaガラス 1
私は、フィンランド出張の際、毎回ドムスの工場を訪れます。窓の打ち合わせは、メールでほとんど済むのですが、最新の製作ラインを必ず自分の目で確かめたいからです。 ヘルシンキから西へ約130Kmレンタカーでの快適なドライブですが、往復やはり同じ景色はつまらないので、帰りは40kmほど遠回りになりますが、小さな町イイッタラに立ち寄ります。 ここは、1881年創業、イイッタラガラスの工場があります。夏場は、ガラス工場を見学できますし、それも結構興味深いのですが、目的は、ショップです。セカンドメイド等の、掘り出し物を探すのも楽しいですし、ダイレクトに日本に送ってもらえるので、たくさん買い物をしたいときは、とても便利です。もちろん、ヘルシンキ市内の店でもタックスフリーで送ってもらえますが、デパートなどでは、階を移しての手続きで時間を取られます。ここは手際が良いし、発送になれているので、順番待ちでイライラすることもほとんどありません。 プレゼントには、箱に入ったプロパーの品が良いのでしょうが、自分の、家で使うものは、セカンドメイドで十分です。黄色いシールの価格のついているものがそうです。さらに赤いシールは各段に安くなっています。ですから、我が家では、日常イイッタラのグラスを使っています。割れたら、また補充すればいいのですから。 昔は、ショップも小さくて、工場以外で一番大きな建物は、ガラス博物館でした。これも、イイッタラグラスの歴史がよく理解できておすすめの場所です。現在は新しいレンガ造りの外観のショップが一番大きな建物になって、以前のショップはレストラン併用になっています。昔のレストランは、別棟の移築したログハウスで、ガラス張りの壁を隔てて、ガラス製品の実演を見ながら食事を楽しむことができました。 ヘルシンキから北へ100Kmの都市、ハメーンリンナからさらに北へ20Kmの小さな町を訪れるのは、14-5年くらい前までは地元の人々に、限られていましたが、今や駐車場も大きくなって夏場には、観光バスが列を連ねて並んでいます。
2010年7月9日 金曜日 ホームページリニューアル
ホームページを更新しようと思っているうちに一年が経ってしまいました。コラムも2009年の4月を最後に休眠状態でした。新しくしたホームページは、当社の主力商品である、木製サッシ、ログハウス、サウナを中心に夫々のカタログをホームページ上でご覧いただけるようにしました。コラムは、今後もできるだけ毎月書き綴りたいと思っています。以前のホームページの引き継ぎが、うまくいかず、何点か欠落しましたが、私なりの、フィンランドへの思いを書いていくつもりです。昔は年に数回訪れていましたので、最新情報も取り入れていたのですが、年に一二度の訪問ではそうもいきません。 40年近く、ただ一カ国にこだわった私の生き方は、多分にえこひいき的な見方があると思いますが、だから日本はだめなんだという結論を導くつもりは毛頭ありません。専門は、建築ですが、建物の見方も建築家のような捉え方ではなく、一般の、フィンランド人、日本人の視点で見ていこうと思っています。青春時代を過ごしたフィンランドですから、その時代へのこだわりは、人一倍あります。ですが、懐かしんで過去の思い出に浸るのではなく、現在、自分が感じていること、説教ではなく、未来を担う若者への期待を込めて、我が国がよい方向へ進むこと、とりわけ私のすんでいる北海道が、自然、気候を共にするフィンランドのように生きていってほしいと、切に願う気持ちち込めて書き続けたいと思います。今は、フィンランド一年で最もよい季節です。成田、関空、中部国際空港とフィンランド航空は、直行便でほぼ毎日飛んでいます。 ヨーロッパ最短、最速の航空会社と宣伝していますが、乗り継ぎの素通りではなくぜひフィンランドへ、足を伸ばしてみてください。
2009年4月4日 土曜日 ヘルシンキ大学 学生寮
仕事を終えて、飛行機への搭乗まで、時間に余裕があったので、新しい市電の路線9番に乗ってみました。懐かしい景色が見えてきました。 1970年代の再開発で、ヘルシンキには珍しかった高層ビル群の地域です。中央駅から列車に乗ると、最初の駅がPASILAパシラ、その右手東側の地区を、イタ(東)パシラといいます。 ここに、建設初期にヘルシンキ大学の学生寮も建てられていました。厳密には、ヘルシンキ大学学生住居供給財団、頭文字をとってHOASといいます。パシラには、ヘッドオフィスのHOAS4があって私は、ここの9階に2年間住んでいました。各フロアー同じような作りで、エレベーターを降りると左右にドアがあってドアを開けると廊下伝いに4室の個室、キッチン、トイレ、シャワーは共用でした。最低限の家具はついているので、学生にとっては多少殺風景でも、快適な生活を送る事が出来ました。地下には、洗濯機、脱水機、乾燥室、アイロン台が完備、10階は、さすがフィンランド、サウナ室、談話室まで整っています。 当時は、市電が通っていなかったので、市バスか、一駅の国鉄に乗って大学へ通っていました。駅舎は、木造の可愛らしい小さな建物だったのですが、今は、歩道橋からも渡れる大きな駅に変身していました。 私は、建築志望のせいもあって、毎日窓から、どんどん出来上がっていくビル群を眺めていました。当時から評判の悪かった高層ビル群、世界的に有名になった1960年代のタピオラ田園都市、職住近接の理想都市計画が、この国の方針だとおもって留学した私にとって、理想と現実の違いを思い知らされる景色でもありました。そんなことを思いながら、市電から眺めるパシラ地区は、懐かしさより、ほろ苦さを感じさせる車窓でした。
2009年3月4日 水曜日 ヘルシンキ市立劇場
ヘルシンキ中心部の湖のような湾、中央駅から北に延びる沿線を挟んで、西側は、トゥーロ湾(トゥーロンラハティ)、アールトの白い大理石のフィンランディアタロが面しています。東側のエラインタルハ湾(エラインタルハンラハティ)には、ティモ・ペンティラ(1931年タンペレ生まれ) 設計による市立劇場が建っています。こちらは、白いタイルが外壁に貼られています。建築に詳しくない方なら、こちらもアールトの建物と勘違いするかもしれません。市立劇場は、1960年の設計コンペによって、ティモが一等を獲て1967年に完成しています。フィンランディアタロの完成が1971年ですから4年前にすでに入り江に建っていました。傾斜地を利用して、大ホール、小ホール、展示ギャラリーから成っています。現在、大ホールは、947席、小ホールは座席がアーチ型に配置されていて、最大9列、437席の配置が可能です。音楽から演劇まで幅広くヘルシンキ市民に活用されています。 築42年を経ていますが、外壁の取替えという大改修を余儀なくされた、フィンディアタロと違って、こちらはしっかりと当時の姿を保っています。 ヘルシンキ中央駅から地下鉄で2つ目の駅Hakaniemiハカニエミで降りるか、地上を走るトラム3B,6番で同じくハカニエミで降車するのも可能ですが、天気が良ければ散歩がてら、歩く事をお勧めします。水辺を伝わるさわやかな風を感じて、グリーンの奥に控えめに見えてくる市立劇場の建物を、美しく感じることができると思います。 この時代、何とたくさんのすばらしい建築家を、この国は生んだ事でしょう。そして、使われ続けている事が、建築家にも、建物にも誇りを持ち続けさせているような気がします。
2009年2月4日 水曜日 お勧めレストラン パレスホテル
前に紹介したガラスパレス(コラムNo41)の設計者、ヴィリヨ・レヴェル(1910-1964)をもう一度取り上げます。ヘルシンキ南港、赤レンガ縞模様の古めかしい市場そばに立つ淡いクリーム色の建物です。1952年完成ですから60年近い、古い建物です。当初は、1,2階産業センター、3−8階ホテル、10階がレストランとなっていました。現在は、1,2階は、いろんな事務所が入っているみたいです。 この建物は、ヘルシンキ中央駅正面に建っている、コンクリート打ちっ放しのビル同様、当時ヘルシンキでは、珍しいコルビジェの影響をいかにも受けているという感じです。駅前のビルは、昨年末訪れたとき、大改修工事中でしたので、昔の面影が残るのかどうかわかりませんが、パレスホテルは、健在です。鉄筋コンクリート造で、1,2階のピロティーの柱、外壁のカーテンウォールは、今の若い建築家は、知らないかもしれませんが、近くで見てみますと、テラゾー(人造石)である事がわかります。港に日が沈みかける頃、夕日に当たるこの建物の表面は美しく輝きます。冬場のわずかな光でもけっこう見栄えがします。 対岸のアールトのエンソのシンプルな白大理石のビルも奇麗なのですが、前にも書きましたが、大理石は、地中海のまばゆい太陽と、紺碧の空がなければ、素地の美しさは、表現出来ないと私は思っています。 この建物2階の手摺り、柱で途切れる事無く使用価値はないのですが、連続しています。設計者のこだわりを感じます。1階のエントランスから中央奥のエレベーターに乗って、最上階へ行きますと、そこはレストランです。港が一望出来ます。冬の凍った白い海もよいですが、夕方、ストックホルムへ向かう大型フェリーの船尾、消えゆく航跡を眺めながらワイングラスを傾けるのも、楽しい一時だと思います。多少、お財布にゆとりがある時、私が、ヘルシンキでお勧めのレストランは、このパレスホテルのレストランともう一つは、レストラン・サボイです。
2009年1月4日 日曜日 ヘルシンキ 古くて趣のある建築散歩 4
ヘルシンキで最も有名な朝市は、大聖堂そばのストックホルム行きの大きなカーフェりーが氷海に浮かぶ南港周辺です。次いで、ハカニエミの朝市、地下鉄で中央駅から2駅目。映画「かもめ食堂」のロケにも使われていました。 この広場から空を仰ぐと北向きに、石造りの塔が見えます。それに向かって坂道を上っていくとカッリオという地区の小高い丘の頂に一段と高く建っている石造りの教会であることがわかります。カッリオ教会です。1906年の設計コンペによってLaes.Sonckラルス・ソンクが指名され、1912年に完成しています。前に紹介した電話会社の建物もそうですが、彼は、すでに学生時代にタンペレ大聖堂の設計で一躍有名になっています。当時は、ヘルシンキ市内で一番高かったと思います。何処からでも見えたはずです。今でも、ホテルの窓から市内を眺めると、冬の遅い日の出、冷気で空気が光って見える彼方に一段高い位置に存在感を示しています。 この教会、通称キヴィキルッコ(石の教会)というのですが、国会議事堂近くの観光客が必ず訪れる岩の教会(テンペリアウキオ)も、高くはないですが丘の上に建てられています。しかし、この時の設計条件は、この地区の雰囲気を変えない事、つまり上ではなく下、地下へ向かうしかなかったのです。時代はもちろん違うのですが、岩と石で随分異なる教会が建ったものだと、少しおもしろく感じています。 同じくヘルシンキのランドマークといえば, 1930年代に建てられた陸上競技場のタワー、リンドグレン、ヤンティーによって設計されたアールト時代の流行の白い建物です。大改修がされて1952年ヘルシンキオリンピックのメインスタジアムとして使われました。 ソンクは長生きで、1956年まで生きましたから、どちらを、ヘルシンキのランドマークと思っていたでしょう。現在、市電9番のルートが新設され、カッリオ停留所で下車すると、すぐそばです。
2008年12月4日 木曜日 サンタクロースエクスプレス
今日はクリスマスイブ。北の町ロバニエミのサンタクロース村は、この不況の中でも、この日に限ってはにぎわっている事と思う。 ヘルシンキから、ロバニエミ市へ行くのは飛行機が一般的。1時間10分で北極圏の空港に到着する。サンタクロース村はすぐそばだ。 列車の旅で行こうとするなら、サンタクロースエクスプレスがいい。ヘルシンキ駅を、19時30分、ロバニエミ駅到着は、翌朝の7時53分、延べ12時間23分の長旅だけれど、個室寝台、二段式寝台、カフェコーナー等設備が整っている。二階建ての白と赤の最新式の車両の個室寝台は、シャワートイレ付になっている。最後尾には、カートゥレインも連結されているので、マイカー持参で旅を楽しむ事も出来る。ただし、出発の2時間前から1時間前までに車を車両に載せておく事が必要だ。 残念ながら、イブの夜は、サンタクロースエクスプレスは、ヘルシンキ駅から出発しない。イブの夜は、国鉄さえ早じまいなのだ。昔、イブの夕方、日本からヘルシンキ空港について、東部の友人宅へ行こうと、ヘルシンキ駅から列車に乗って程なく、車掌さんにこの列車は、ここで今日は終わりですと降ろされた記憶がある。日本では考えられない事なので、ここで路頭に迷うのかと思ったけれど、そこは、親切なフィンランド人。友人宅の住所を伝えると電話で連絡をとってくれて、我が家のクリスマスも楽しんでいきなさいと、自宅に招待してくれて、友人も2時間の冬道を、迎えの車を飛ばして来てくれた。 フィンランドのクリスマスには、思いでがいっぱいだ。そんなことを考えながら一度サンタクロースエクスプレスに乗って、ロバニエミを訪れてみたいと思っている。ちなみに今年の、列車の料金は、一般シートで約1万円、二段ベットで、1万5千円、個室で2万3千円という所です。この国は、広広軌といって日本の新幹線よりも広い線路幅なので、乗り心地はいたって快適。車窓からの冬景色を楽しみながらといっても、ずーっと暗い白い大地を、延々見るだけの冬の旅になってしまう。
2008年8月4日 月曜日 トゥルク ユロスノウセムス(復活)礼拝堂
ヘルシンキから西へ190Km、フィンランドの古都トゥルク。人口17万5千人のこの町は、13世紀から建設が始まり1812年にヘルシンキに移されるまでこの国の首都であった。この町の南西に位置するトゥルク市営墓地に建っている礼拝堂を今回は紹介したい。建築に興味を持っている方なら誰でも知っている世界的な建築家アルバー・アールト。 同時期の建築家で、彼との共同作業もあるエリック・ブリッグマン、生まれは、アールトより7年早く、1955年に64歳で、アールトより20年も前に他界している。トゥルク大学の教授でもあって、市内にはいくつもの大学、アパート等の設計をしているが、日本人には、あまり知られていない。フィンランドでは、教会は、kirkko(キルッコ)礼拝堂は、kappeli(カッペリ)と言う。ユロスノウセウスカッペリは、親族が、埋葬される前に最後のお祈りを捧げる所なので、墓地の中にひっそりと建っている。外観も質素で決して自己主張はしていない。1939年の設計で、完成は1941年。中に入って、空間の使い方の、みごとさにおどろかされる。 私が最初にここを訪れた時、中世のヨーロッパのロマネスクに、光が加わったという印象を感じた。モダンな近代建築ではなく、主要構造が鉄筋コンクリートなのに、石造りの教会が光をまして、中世からタイムスリップして来たような強い衝撃を覚えたのを、今でも昨日の事のように思い出すのです。時を変えて訪れると、祭壇に注ぐ光の角度が、季節を感じさせてくれて、空間の表情を幾重にも増すのです。いくら言葉を連ねようと、この空間の素晴らしさは、礼拝堂の中に建って自分で感じてもらうしかありません。機会があったら、ぜひ足を伸ばして観ていただきたい。
2008年7月4日 金曜日 ヘルシンキ 古くて趣のある建築散歩 3
6月21日の夏至を過ぎて、日没は理論的には早くなっているはずだけれど、白夜は未だ真っ盛りの感。石畳に蓄積された暑さを肌に感じる。エスプラナーディ公園通りの右側(車は一方通行港方向)を港に向けて歩き、二番目の通りを右へ曲がると、緩やかな上り坂のkasarmiikatuカサルミカトゥに通じる。150M程歩くと右手にグレーの石造りの建物と緑色のホテルの文字と入口のテント布が見えてくる。ホテル リヴォリ。 左手は、広場になっていて、平屋のスーパーマーケットが見える。この建物Karl hard によって1899年に設計され、完成は1901年。そもそもは、国の教育機関、日本でいうと文部科学省の建物。当時流行の建物の角を出窓のように飛び出させた、ベイウィンドゥのような、尖塔のようなアクセント、ヘルシンキ市内を気にして歩いてみると随分と見受けられる。決まってこの時代1895年から1915年の建物に多い。いつの時代からホテルになったかは、わからないが客室55室のホテルとしては、小さなクラシカルな、高級ホテルだ。ラウンジ、レストランともとてもクラシカルだ。少し話は、この建物とそれるが、ホテルの正面に位置するマーケット広場の平屋の建物(実際は、広場坂になっているので地下になる一部2階建)、1970年代は、フィンランドデザインセンターとして多くの観光客でにぎわっていた場所である。 フィンランドとの直行便も無い時代、アンカレジー経由あるいは、南回りでコペンハーゲンで乗り継ぎ、さらにヘルシンキへと足を伸ばした日本人の建築、芸術に携わる団体の人々は、決まって観光バスの見学ルートに入っていたここにバスを連ねた。北欧デザインの色彩、シンプルな造形に感激した時代の、最先端の品々を展示していたのが、現在のこのスーパーマーケットなのだ。そんな当時の情景を思い浮かべて、このホテルに部屋を取り、窓越しにこの広場を眺めたら、北欧に憧れた、明るい未来を予感した時代がよみがえってくるような気がする。